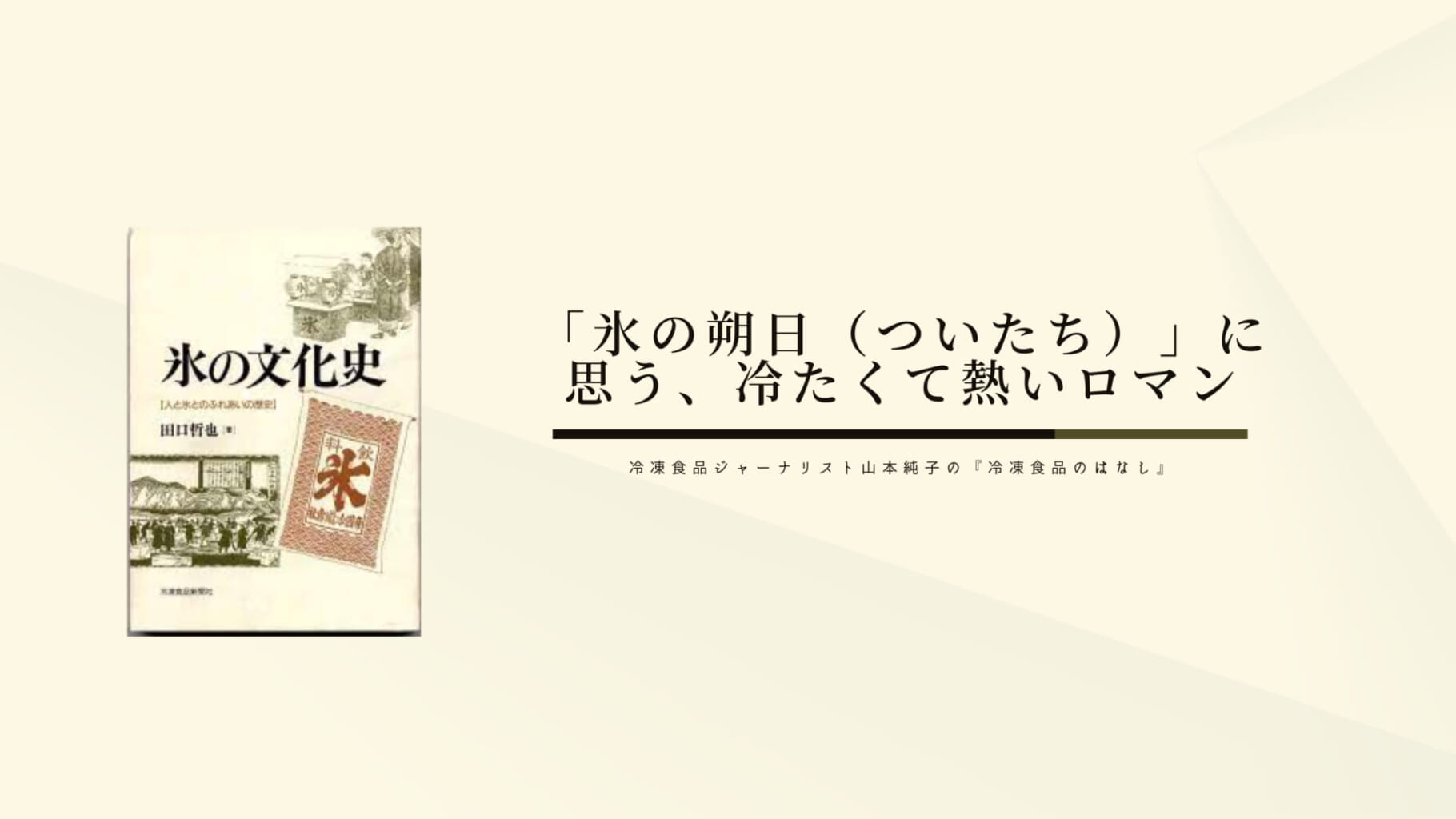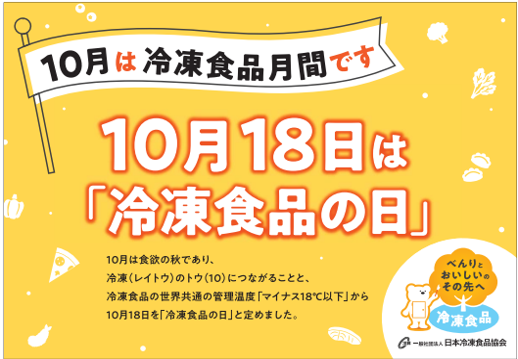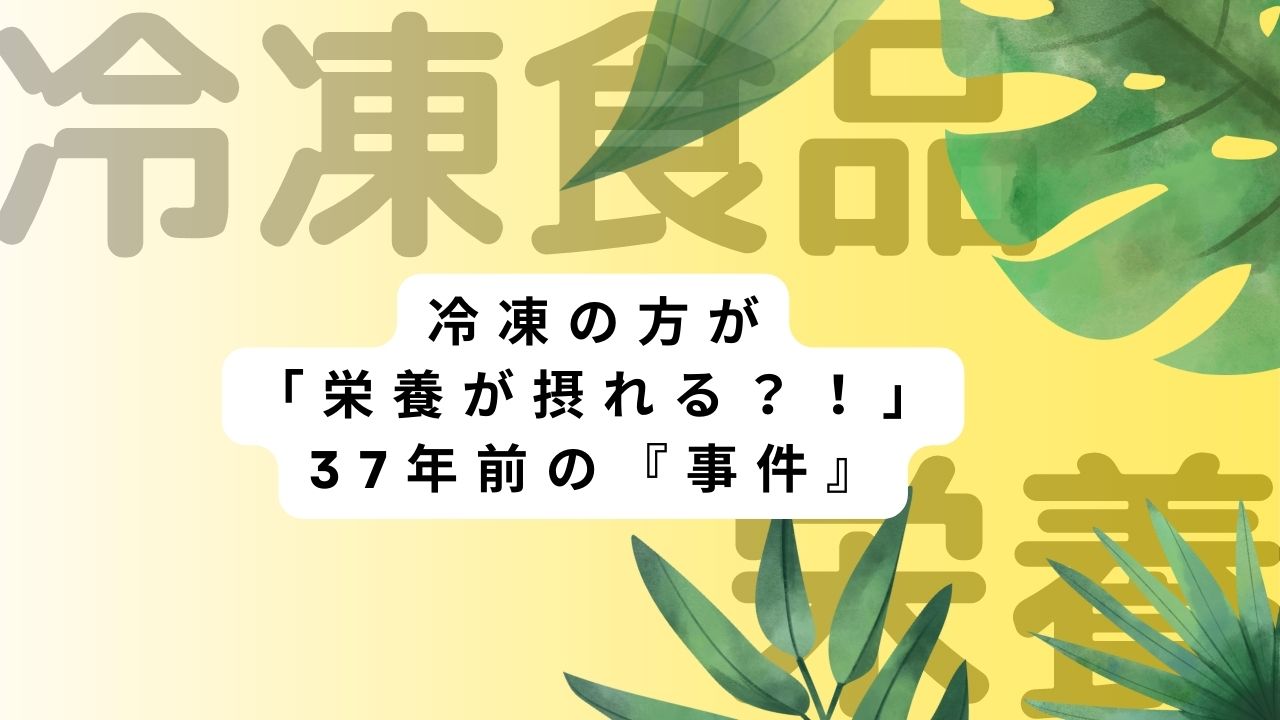- 2023年7月20日
暑い夏を「冷凍食品」で乗り切ろう!
2023年夏の東京は、梅雨明け前からの猛暑続きでバテバテの方続出(私見です)、先日出演したFMラジオ番組では、「出かけたくない!」時に便利な、レンジ調理で楽しめる“老舗のあじわい”冷凍食品、そして、約3分レンジして半解凍のタレとまぜると冷え冷えの麺ができる、ニチレイフーズの「冷やし中華」(酢醤油だれ/ごまだれ)をご紹介しました。予想通り、感動の嵐!!でした。 暑いから家でごはん、というときに、間に合わせの料理ではなく、松屋銀座の「ギンザフローズングルメ」で買っておいた『銀ぶらグルメ』や『浅草グルメ』シリーズをチンして幸せ気分。そして、冷たい麺も台所で火を使い、汗を流して作らなくてもOKなんて、冷凍食品の世界はどんどん進化しています。 ▼ニチレイフーズ「冷やし中華 ごまだれ」の調理過程 ▼松屋銀座「浅草グルメ 鳥安 あひ鴨葛餡がけ 七味仕立て」 ■まずは、コールドチェーンをチェック 今回は、暑い夏を冷凍食品で乗り切ろう!という話題。では、どんな冷凍食品がオススメ?というその前に、まずは、重要なコールドチェーンのチェック!です。 お店から家までの持ち帰りは、ぜひアイスクリームを思い浮かべてくださいね。炎天下にアイスをそのまま15分も持って歩いたらとけてしまいます。-18℃以下で保管・流通する冷凍食品も同様なのです。しっかり保冷マイバッグに入れて、ドライアイスや保冷剤を利用しましょう。そして帰宅したら、すぐ冷凍庫に。 さて、ご家庭の冷凍・冷蔵庫。季節による温度切替え機能がありますが、ご存じでしょうか? 冬期と通常~夏、季節によって冷蔵庫のパワーをセットできます。「大」「小」の切替えが付いているかもしれません。それが「冬期」のままになっていませんか?真夏に向けて要チェックです。 そして冷凍庫の開け閉めは手早く! PiPiPiとアラートが鳴るまで開けていたら、庫内の温度が上がって食品にダメージを与えてしまいます。素早く開け閉めするには、どこに何が入っているのかしっかり把握しておきましょう。今のうちに、きちんと整理しておくのも一手ですね。 ▼詳しくはこちらの記事もご確認ください! ■夏の傾向:お弁当減少、ランチ需要アップ 家庭用の冷凍食品が、お弁当需要中心に品揃えされていた10年位前までは、夏休みシーズンになると売場の品揃えは少し変わり、アイスとの境界線が移動してくると共に、お子様向けランチに米飯類や麺類、ピザ・スナックなどが充実していました。近年は、冷凍食品の売場スペースが広がったことで、夏だからといって以前ほど大きな変化は感じないかもしれません。実際、麺類の新揃えは、近年注目されているラーメンも加わって、ますます充実しています。夕食向け惣菜、外食気分の品揃えも増えています。腐らないからムダが無い冷凍野菜の人気も続いています。 夏場は、ビールのお供のおつまみ系、爽快感を求めてピリ辛系の品揃えが加わるはず。ぜひチェックしてください。 夏向きの麺、米飯、ピザ・スナック類に加えて、今年の夏に注目したいのは、『ワンプレート』商品。『ワンプレート』とは、おかずの主菜と副菜がセットされた商品や、主食と主菜・副菜がセットされたお弁当スタイルの商品です。少し前までは、ブランドメーカーではニップンの独壇場とも言ってよいほどのジャンルでしたが、大手メーカーが次々と参入してきました。 この『ワンプレート』冷凍食品の市場規模は、5年で300%、つまり3倍になったと推計されています(2018年→2022年、インテージSCIデータからニチレイフーズが推計:7月12日会見より)。 往年の業界人は、ワンプレートと聞くと、アメリカで一時期ブームになった「TVディナー」を思い浮かべますが、時代は変わり、テレビに夢中なので間に合わせのレンチンディナーというかつてのイメージではありません。きちんと美味しく、使用具材もバラエティ豊か、そして栄養バランスも配慮されているという、至れり尽くせりのセットメニューが近頃の『ワンプレート』です。 『ワンプレート』以外にも、トレイ付きの具付き麺類、トレイ付きのごはん類など、ランチ需要をつかんでいる商品群があります。コンビニ各社も、パスタ、カレーライス、丼タイプ商品をはじめ、『ワンプレート』の商品開発に力が入っています。 『ワンプレート』は、在宅女性のランチ需要を中心に伸びてきましたが、今後、子どもたちが1人で家にいるときのごはん、というニーズ、お料理が苦手なシニア層のニーズもつかんでいくことでしょう。1人で家にいて火を使わず安全に調理して、栄養バランス良く食べて、後片付けも簡単、もちろん美味しいという満足度の高い商品が揃っています。 ■にんにく、しょうが、ホームフリージングで無駄なく 夏のスタミナ、といえばにんにく。先日もわが家では、“ニンニクマシマシ”の「大阪王将 羽根つきスタミナ肉餃子」を食べて、初期夏バテ防止を図りました。夏を元気に過ごすパワーチャージを期待して、スタミナ料理に大活躍のにんにく。でも、生のにんにくは、うっかりしているとシワシワ、カチカチに。そんな経験をしている方には、ホームフリージングをオススメします。 「よし、スタミナ料理だ、にんにく!」とひとかたまりや一袋買ってきたときには、その日から数日内に使う分以外は冷凍しましょう。にんにくは1片ずつ薄皮付きでラップしてジッパーバッグに入れても良いですし(凍結していても結構簡単に皮むき、スライスができます)、調理するときにもっと便利に使いたい、ということでしたら、スライス、みじん切り、おろしなど好みにあわせて一気にカット(手袋オススメ)、料理1回分をラップしたものをたくさん作り、さらにジッパー付きバッグに入れておきましょう。とても便利です。 例えばイタリアンなら、オリーブオイル・冷凍スライスにんにくをフライパンに入れて、加熱すれば、生にんにくと同等レベルで香りが立ってきます。 同じように、しょうがもひとかたまりを全部使い切れずに、水分が抜けてしまうなど様子が悪くなって捨ててしまった、という経験があると思います。これもフリージング! にんにく同様、細切り、千切り、みじん切りなどにして保存しておくと、ロス無く使えます。切って冷凍するのが面倒な場合は、そのままラップに包んでジッパー付きバッグに入れて冷凍します(実は山本流)。この場合、少し初期投資の強靱なおろし金を買っておきます。いざ使うときには、冷凍庫から取り出し、ラップの端をすこし開けてガリガリと必要量をたくましいおろし金ですりおろします。塊はそのまま、冷凍庫に戻します。これも便利ですよ。夏場の生姜焼き、そうめんの薬味に、冷凍うどんをレンチンして冷水で締めたメニューにと活躍します。 ■夏の「うどん」 コスパとタイパでますます盛り上がりそう 冷凍うどんのレンチン、冷水締めの話題に繋がりましたので、最後は冷凍玉うどんのアレンジメニューのはなし。 冷凍うどんはかつて、冬場に売れて夏場は需要激減という、いわば季節商品的な冷凍食品でしたが、2014年あたりからテーブルマークが「レンジで解凍OK」をPRして、夏場も売れる人気商品になりました。つまり、火をつかって茹でて、水で締めるという作業からの解放。冷凍うどんの個包装パッケージをレンジでチン(1食約4分)、水で締めればOK。あとは、夏野菜など好みの具と好みのタレ(ドレッシングでもOK)をかければ、涼をとれる麺料理の完成となります。 実は、冷凍玉うどん、昨年あたりから需要急伸しています。食品の価格がどんどんアップする中で、冷凍玉うどんは価格がアップしても1玉60円~80円くらい。手軽でコスパもタイパも良い主食として人気なのです。確かに、具を足して、めんつゆなど添えても、1食200円以内でしょうか。 日本冷凍めん協会のホームページが先日大幅リニューアルされて、アレンジメニューがますます充実、見やすくなっていますので、ぜひチェックしてみてください。 https://reitoumen.gr.jp/ ちなみに、夏うどんメニューの私のお気に入りは、納豆、冷凍おくら、冷凍とろろなど一気に乗せるネバネバうどん。希釈タイプのめんつゆをかけて、青い野菜がほしいなと思ったら、冷凍きざみねぎ。生鮮でも、きゅうりのさいの目切りとかカイワレなど簡単なものがオススメです。 ▼夏におすすめのネバネバうどん 夏に負けない!「ネバーギブアップ!」とおやぢギャグ的なノリで食べます。