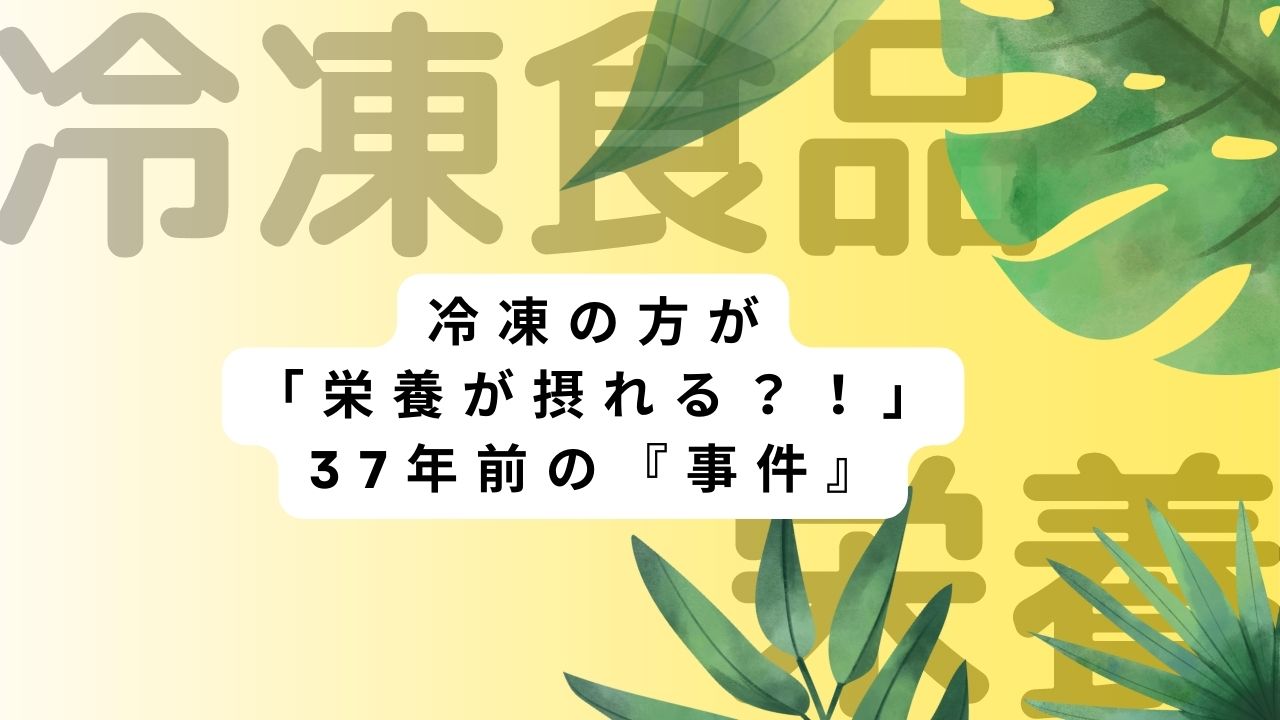- 2024年10月22日
イートアンドフーズ関東第一工場の従業員食堂は「フローズンフーズラボ」
今回は、ちょっと趣向を変えて、イートアンドフーズの関東第一工場(上田浩司工場長)の従業員食堂ルポです。 じゃあ、冷凍食品を使ったメニューを出す食堂ですか?って。いえいえ、それは普通の事業所給食。ここは、従業員が冷凍ショーケースから自分の食べたい冷凍食品を選び、レンジでチンして食べる食堂です。隣接して厨房もありますので、もちろん「大阪王将 羽根つき餃子」を焼くこともできます。 名前もかっこよく「FROZEN FOODS LAB(フローズンフーズラボ)」。今年7月、同工場3階に完成したばかりです。 ショーケースに陳列されている冷凍食品は、同社工場で製造している「大阪王将」ブランドの商品はもちろん、普通にスーパーで販売している冷凍食品メーカー各社の人気商品もたくさん。冷凍食品をいろいろ食べながら、研究していこう!という気持ちが伝わってきます。 実際、食堂のすぐ隣は、同社の商品開発室(ラボ)です。しかも仕切っている壁は全てスケルトン。従業員一丸、工場で働く人が一体となって、「良い冷凍食品、美味しい冷凍食品を目指す」意気込みを感じました。 自社製品だけじゃない!福利厚生も兼ねてリーズナブルに提供 冷凍ショーケースの中を見ると、ランチにぴったりな流行りのワンプレート冷凍食品各種をはじめ、炒飯、ピラフ、ラーメン、焼そば、パスタなどなど30品ほど。ライスバーガー、キンパ、今川焼といった小腹を満たすスナックもあります。 そして、価格が「安い!」 「従業員の福利厚生も兼ねていますから」と森下賢人ライン長(写真上㊨)。調達・生産管理を担うのが仕事ですが、「フローズンフーズラボ」の管理も担当しています。 上田工場長(写真上㊧)は、「従業員がより働きやすい工場にしよう、ということで投資もしてもらった」と説明して下さいました。 第一工場3階には事務所と開発室、そして以前は外食店舗「大阪王将」をイメージした厨房と食堂はありましたが、従業員の食事を提供する機能は無く、みなお弁当持参か仕出し弁当利用。もしくは、道路を隔てた関東第二工場の社員食堂に行っていました。工業団地内ですので、周辺に飲食店はありません。「フローズンフーズラボ」ができて、食事の不便さが解消されたわけです。 実は同工場は昨年12月に出火が発生し、従業員は全員無事に避難できたのですが生産ラインは大打撃。食堂の3階もススだらけになったそうで、改修に時間を要しました。 生産設備は一部、すぐ復旧作業に入り、今年4月には外食店舗向けの麺製造ラインと冷凍食品の水餃子2ラインが稼働開始しています。その他冷凍食品4ラインのスペースは工事中で、そのうちの3ラインは2025年2月に稼働開始を予定しています 先日、本社で仲田浩康社長による第2四半期決算説明会席上、来年稼働する生産ラインについて説明がありましたが、2ラインが餃子ライン、残り1ラインは新たな「お惣菜ライン」とのこと。今注目を集めてマーケットが伸長している、ワンプレート商品にも挑戦していく方針です。 生産の中断は工場にとって大きな痛手ですが、それがバネになっているかの様な、チャレンジ意欲を感じさせてくれるのが同社の素晴らしいところだと思いました。 冷凍食品を実食して研究していくから「ラボ」 お昼時におじゃまして、従業員の皆さまが商品を選んで、チンして食べる様子を拝見。無人販売ですので、冷凍食品を選んだら、それを持って自分のIDでコンピュータ登録。そしてレンジのコーナーに行って調理します。加熱している間は、フリードリンクコーナーに行って青汁やお茶を用意したりします。1食の調理はだいたい長くても7分程度ですから、携帯メッセージのチェックなどしていたら、あっという間ですね。 仕事に入る前、休憩時間に、また帰りがけにと何度利用してもOKです。また、自宅から持ってきたお弁当箱をチンしている方も。自宅から持参したごはんを温め、おかずは冷凍食品を買う、という人もいるそうです。 お昼どきなので、ワンプレート商品を選んで食べている方が多かったです。ピラフ1袋を一気に食べるという強者も!!。 ショーケースの中には、小分け調理して残りに名前を付けて保管するスペースもありました。やはり、冷凍食品は無駄がなくて便利。 ぜひどうぞ、と言われ、私もイートアンドフーズの皆さまと一緒にランチタイム。私がショーケースから選んだのは、「大阪王将 天津飯」。また、併設のキッチンで焼いてもらった「大阪王将 羽根つき餃子」と、ニンニクマシマシの「大阪王将 羽根つきスタミナ肉餃子」も一緒に頂きました。 やはり、「大阪王将」店舗の人気コンビネーション。ベストマッチでした。 上田工場長、森下ライン長も自社製品をチョイス。やはりこれは「愛」ですね。もちろん日常は他社製品もいろいろ食べているそうです。「ちょっとくやしいけど、他社のも美味しいですね。負けずにがんばります」と上田工場長。 なるほど、「フローズンフードラボ」の狙いはもう一つあって、来年春から稼働させる新ジャンル「お惣菜ライン」の成功に向けて、従業員全員のイメージ醸成の役割も担っているようです。 日本アクセスの「チン!するレストラン」をヒントに この従業員食堂、「フローズンフードラボ」のモデルとなったのは、日本アクセスのイベント「チン!するレストラン」でした。 スーパーの冷凍食品売場のような冷凍ショーケースから、自分の食べたいものを選んで、すぐにレンジでチンして食べられる楽しいレストラン。日本アクセスが主催する「フローズンアワード」の10周年記念イベントとして、2021年に秋葉原で開催したのが始まりです。 イベントといっても、お客さんがお金を払って参加する時間制の食べ放題レストラン。それが大変な話題になり、2022年は大阪・梅田で、2023年は名古屋で開催しています。いずれも大盛況。キャンセル待ちも今年は1万人を超えたと聞いています。 本欄でも取り上げましたが、このイベントにインスパイアされて、昨年12月には、大阪・戎橋に常設の冷凍食品・アイス食べ放題レストラン「レンチン食堂」(運営:カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)が日本アクセスの全面協力でオープンしています。 イートアンドフーズも「チン!するレストラン」のスタイルを参考に、関東第一工場3階を復旧するにあたって、従業員食堂にと思いつき、日本アクセスに相談を持ちかけたそうです。同社フローズンMD部の松元雄一部長もその発想を喜び、同社展示会場のフローズンコーナーに写真で紹介しました。 「ストックする冷凍設備は十分にありますから」と森下ライン長。確かに、ショーケースに入れる以外の段ボールに入った製品を冷凍庫の一角にストックしておくのは簡単。「1回の発注は40ケースほど。ほぼ1週間分くらいです」とのこと。冷凍食品だからこそ、効率よく無駄なく商品供給ができるわけですね。 “ええもん”を作る発想力を育てる工場へ 「チン!するレストラン」から従業員食堂を思い付くなんて、やはりすごい発想力だなあと感心します。今年55周年を迎える「大阪王将」のDNAなのでしょう。美味しいこと、楽しいことに一生懸命。店舗に来てくれた人、冷凍食品を買ってくれた人に対して、思いっきり喜んでもらいたい、という気持ちが前面に出てくる企業です。 上田工場長は今年3月に着任。つまり関東第一工場の新たなスタートを託された方です。水餃子ラインの稼働、その他内装復旧工事、そして、餃子ライン、新ラインの工事、稼働へと忙しい日々です。強い思いは、より働きやすい工場、さらに製造能力は1.5倍を目指すということ。「うちのいいところは、くじけない、ということです。ええもんを作る、美味しいもんを作る。他社には負けませんよ」 さらに上田工場長「働く人がやりがいを見つけられる工場、仕事が楽しいと思える工場を目指しています。食品を製造することを通して自身の成長を実感できる教育に力を入れます。人と人との関係の豊かさを実感できる工場に」と熱い思いを語ってくれました。 気になる人気商品は、、、 さて、イードアンドフーズ関東第一工場で働く方々に、どんな冷凍食品が人気なのか、気になりますね。ということで、直近のベスト3を聞いてきました。 ★第1位 ニップン いまどきごはん 具だくさんビビンバ なんと、ビビンバが№1。確かにその名の通りの具だくさん(具5種類で100g以上)で野菜たっぷり。健康的なワンプレートをセレクトする、意識高めの方が多いのではと推察します。実際にシリーズの人気商品です。 ★第2位 ニッスイ ふっくらごはんとチキン南蛮 ニッスイ『まんぞくプレート』シリーズの1品です。これもなるほど。コシヒカリブレンドの釜炊きご飯が輝くほどに美味しいシリーズなんですね。森下ライン長によると、から揚げなども含めてチキンのおかずは大人気なのだそうです。 ★第3位 bibigo 本格やみつきたれのプルコギキンパ これは驚き、Kフードがランクインです。CJ FOODS JAPANのキンパシリーズの1品。本場の味わいを再現した甘辛のプルコギたれ、野菜もたっぷりのキンパです。 皆さま美味しいアイテムをよく分かっていて、しかも野菜多めを選ばれているようですね。「フローズンフーズラボ」で無料提供している青汁と合わせれば無敵のランチ。休憩後の仕事もがんばれそう。 皆さま、取材にご協力を頂き、ありがとうございました! ごちそうさまでした!